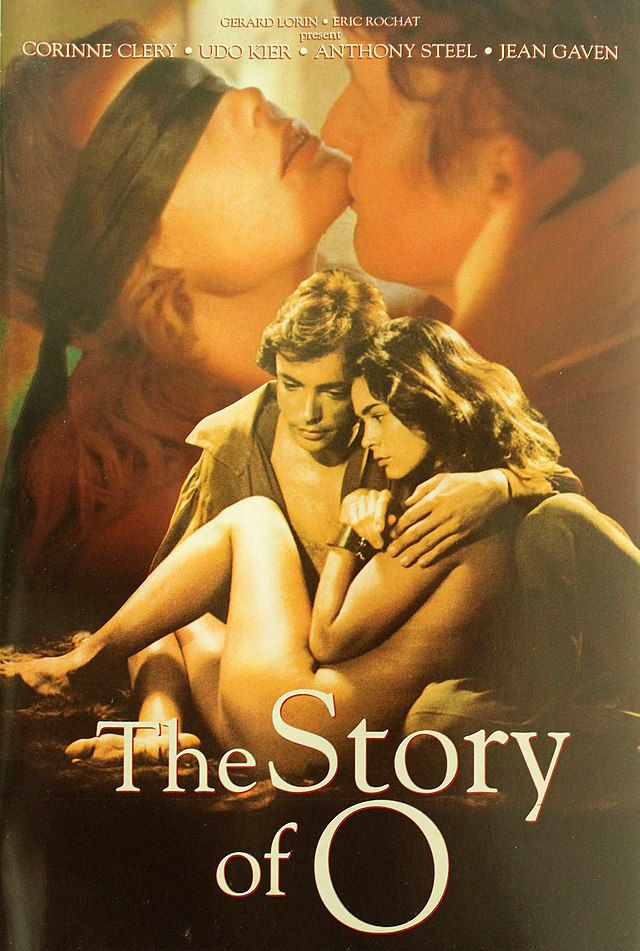今夜はジャズに酔いしれたい
- 香月葉子

- 2021年11月23日
- 読了時間: 10分
更新日:2024年7月20日
女性のジャズ歌手には好きな方がたくさんいます。
たとえばジュリー・ロンドン(Julie London)。
たとえばシャーリー・ホーン(Shirley Horn)。
たとえばベティー・カーター(Betty Carter)やエラ・フィッツジェラルド (Ella Fitzgerald)。

彼女たちひとりびとりの特徴と魅力については、音楽評論家の方たちが書かれたものをお読みになったほうが、はるかにしっかりとしたイメージを得ることができるのではないかとおもいます。
ですから、じつは、べつのことをお話しするつもりで、これを書きはじめたところなのです。
それにしても、音楽をことばで説明しなければいけないなんて、音楽評論家の方たちは、なんてむつかしいお仕事をなさっているのでしょう。
詩的なたとえをつかったり、ほかの曲と比較したり、演奏家について語ったり……。
ある楽曲についての解説文をお書きになっている方は、いろいろな手法をつかって、わたしたちにその音楽のジャンルや曲(tune)のイメージがうかぶように力をつくしていらっしゃいます。
それでも、読者ひとりびとりがもっている音楽のジャンルにたいする好みやこだわりと、読者の記憶のなかに残されている曲数にたよるしかないのですから、たいへんなご苦労をなさっていることはまちがいありません。

「このサビの部分はあの人の演奏するあの曲のああいう感じに近い」とか「このリフはあのグループがどこどこで演奏したときに使われていたのと同じようなノリがある」とか「この曲にはいままでにないグルーヴ感がある」といわれても、それに関する情報を共有していない読者にとっては、比較されているもの同士のつながりがまったくわからないということにもなるでしょう。
けっきょく「どんな感じの曲なのか想像もつかない」という方だっておられるでしょう。
すべてはその解説に目をとおしている読者それぞれの音楽的教養にたよるしかないからです。
読者のがわにその用意がなければどうしようもありません。
音楽評論家がお書きになった解説を読んだあとに、その曲を耳にした読者から「じっさいに、例の曲を聴いてみたのだけど、あなたが説明していた曲のイメージとはまるでちがっていた」と言われてもしかたがないことなのです。
そうかといって音楽理論をひきあいに出したら、わたしのような一般人には、なんのことだかますますわからなくなります。
たとえば、属7の和音がどうのとか、長6度の減3和音をつかっての即興演奏だといわれても、まるでロゼッタストーンにきざまれていた古代エジプトの象形文字を解読してみてください、と言われるようなものです。
ですから、音楽評論をなさっている方は、ほとんどの場合、そのアーティストの生い立ち(おいたち)や、そのアーティストをとりまいている時代の空気、他のアーティストたちとのかかわり、またはそのアーティストがインタビューで残したことば、そして、ときには読者の興味をそそるようなアーティストの個人的エピソードなどを語ることで、そのアーティストの輪郭(りんかく)をつくりあげてくださいます。
つまり、その音楽への入口をつくるだけではなく、聴いたあとに「なるほど」とうなずける出口をも提供してくださっているのです。
わたしたちの知的好奇心をじょうずにくすぐりながら……。
わたしが若いころは、レコード店に足をはこんで試聴させてもらっていましたが、いまではあらゆる楽曲を YouTube や Spotify や SoundCloud でダイレクトに試聴することができます。
そのため、音楽評論家の方たちの文章にふれる機会がすくなくなって、わたしはさみしい思いをしています。

キース・ジャレット(Keith Jarrett)という、もう形容のしようがないほどの才能と技術をあわせもったピアニストがおられますが、たしかに、あの方のおっしゃるとおり「音楽をことばであらわすことはできない」というのはほんとうだと思います。
けれども、ある音楽家や楽曲とのつきあいは、Live や Club で、あるいは YouTube や Spotify や SoundCloud などで、ぐうぜんにその音楽にふれる機会がもたらしてくれるものばかりでもなくて、ラジオなどで耳にした解説や、どこかの雑誌やウェブサイトで目にした解説文にさそわれてはじまることだって多いのではないでしょうか。
たとえば『一生にいちどは聴いてみたいジャズピアニスト50人』とか『恋人とお部屋で踊るためのエレクトロニカ特集』とか『寝苦しい真夏の夜にぴったりのR&B20選』などという記事につられて、音楽評論家や解説者の方たちからいままで知らなかったアーティストや曲を教えてもらい、「ためしに聴いてみようかな」と楽曲をダウンロードすることのほうが、新しい音楽にふれるための近道かもしれません。

ところで、ここまで書いてきたわたしは、はじめに意図したものとはすこしばかりちがうお話しをしてきたことに気づかされました。
じつは、つぎのようなお話しを聞いていただきたかったのです。
たとえば、楽器を演奏する方でパット・メセニー(Pat Metheny)という方がいます。
ギタリストです。
先に紹介させてもらったキース・ジャッレットとおなじように、とてもひとつのジャンルにおさまるような音楽家ではありません。
そのパット・メセニーが即興演奏をはじめると、その楽句(phrase)が、わたしのような素人には、どうしてもジョン・コルトレーン(John Coltrane)という方がサックスを吹いているかのように聞こえるときがあったりして、もしかしたら、ほんとうにそうなのかしら、それともわたしの耳がおかしいのかな、と小首をかしげてしまうのです。
くわしい方に教えていただきたくなります。
音楽評論家の方たちに説明していただきたくなってしまいます。

それから、さきほどのキース・ジャレットなのですが、即興演奏に入って、あの方独特のフレーズをとんでもない速さで右手が奏でているとき、左手できざまれるあの方に特有のリズミカルな和音に耳をすませていると、ベースとドラムとのトリオなのに、なぜかサイドギタリストがいるかのような不思議な感覚がしてきて、わたしの耳がおかしいのかしら、と、ひとり、肩をすくませてしまいます。
話はかわりますけれど、芸術の歴史をふりかえってみますと、フランスの詩人マラルメは作曲家のドビュッシー(Claude Debussy)にさまざまな影響をあたえたそうですし、あらたな光学理論を知ることによって画家のスーラやモネは点描という技法をつかうようにもなりました。
幼いころに教科書で学んだ、白光(はっこう)とも呼ばれるお昼間の太陽の光が、じつは7色のスペクトラムからできあがっている、という理論です。
このように、画家が新たな科学理論から影響をうけたり、作曲家が新しい詩人の作品から過去にない楽曲をうみだしたり、また、いままでにない音楽を耳にした詩人たちが、いままでにないことばの組み合わせやリズムをもちいて、その音楽に近づこうとすることだってありました。
音楽や詩や絵画というジャンルをこえてアーティストたちがおたがいに影響をうけたりあたえたりすることはとても自然なことのようです。

でしたら、楽器のちがいをこえておたがいに影響をあたえたり受けたりすることだって、とうぜんのことだと思います。
あるピアニストが好んで使っていたフレーズをギターで奏でたり、あるサクソフォニストに特徴的なフレーズをピアニストが取りいれたりなど……。
ときには性別というボーダーをこえて影響をあたえたり受けたりすることだってあるはずです。
これも、わたしのおかしな耳のせいかもしれませんが、レッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)をはじめて聴いた当時、そのグループのヴォーカリストであるロバート・プラントという方の歌唱法が、どうしてもジャニス・ジョプリン(Janis Joplin)を思いおこさせてしかたがありませんでした。
とくにシャウトしたときには、27歳の若さで亡くなったジャニス・ジョップリンがお墓のなかからよみがえってきて、パワフルに叫んでいるかのような錯覚をうけたりもしました。

ジャズの歌手にダイアナ・クラール(Diana Krall)という方がいます。はじめに名前をあげましたシャーリー・ホーンという女性ジャズシンガーと同じくピアニストとしてもすばらしい方です。
ところが、ダイアナ・クラールの声に心をうばわれてうっとりしているとき、その歌い方のほうに耳をとられてしまうと、なぜかフランク・シナトラの男性的な顔が目にうかんでくるのです。
不思議でなりませんでした。
とくにダイアナ・クラールの歌詞の区切り方に耳をすませたときにはそうでした。後期のシナトラの、なんとなく投げやりで大胆にすら聞こえる歌いっぷりにそっくりなのです。
注意して聞いてみると、あまり〈こぶし〉や〈ビブラート〉を使わず、とてもストレートで、かなり男性的な印象をうけます。
小説に置きかえて考えてみますと、〈形容詞〉と〈副詞〉をできるかぎり排除したヘミングウェイの文章テクニックに近いものを感じさせられます。
つまり男っぽい節回し(ふしまわし)なのです。
ですから、彼女の歌を聴くたびに、なぜか、フランク・シナトラの、あの飾らずに歌っているようでいて、わたしたちの心を暖かくつつみこんで心にしみこんでくる、なんともいえない繊細な歌唱法を思い出さずにはいられなくなるのかもしれません。

そんなことを考えているうちに、ふと気づかされたことがあります。
性別のちがいを芸術がとりいれることはあっても、芸術そのものは性別を問わないのだ、と。
たぶん、このことが言いたかっただけなのかもしれません。
それなのに、こんなところまで来てしまって、こんな場所で迷ってしまいました。
でも、そうは言いながらも、わたしは、書いているときのこの独特な〈なやましさ〉を楽しんでいるのかもしれません。
書きつつ考えるせいなのか、わたし自身、書いたものに教えられることがたくさんあります。
わたし自身が知らなかった自分、気づかなかった自分に出会えて、おどろかされることもあります。
ジャズの音楽家がおっしゃる即興演奏(improvisation)ってこんな感じなのかな、なんて想像したりもします。
演奏家の方たちがそれぞれの楽器で対話をしたり、観客の反応にたいしてリアルタイムで受け答えをするようなことは、モノを書いている人間にはできないことなのです。
書いているときは、いつも、ひとりきり、なのですから。
ですから、かけあい(interplay)をする相手も、このわたしひとりしかいません。
それでも、頭のなかには数人の自分と過去の偉大な作家とわたしが夢に見ている読者の方たちがいて、さまざまな会話や対話をかわしつつ、思考のキャッチボールをはじめたりしますので、たくさんの異なる声が聞こえてきて、おどろくほどにぎやかで忙しいのです。
ほかの方たちから見たら、ほとんど〈狂気のさた〉かもしれません。
狂人と変わらないのかもしれません。
たえず過去の亡霊たちに憑依(ひょうい)されているわけですから。
そのため、頭のなかでは、わたしが夢に見ている読者の方々をもふくめて、たしかに、老若男女(ろうにゃくなんにょ)さまざまな声が聞こえています。
でも、ひとりであることに変わりはありません。
そして、モノを書く人間にとっては、もしかしたら、この〈ひとりきり〉という状態こそが音源そのものなのではないかとも思っています。
いえ、この〈ひとりきりの状態〉こそが、ことばを演奏するために必要な、もっとも大切な楽器のひとつなのかもしれません。
このような孤独(solitude)は、ときに、とても良い音色を奏でてくれます。
無断引用および無断転載はお断りいたします
All Materials ©️ 2021 Kazuki Yoko
All Rights Reserved.